ご家族やご親族など身近な方が亡くなると、相続が発生します。
相続手続きや相続税申告は人生の中でも経験する頻度が非常に低いため、手続きに不慣れな方が大半ではないでしょうか。しかしながら、ひとたび相続が発生すれば、一定額を超える遺産を相続した方に相続税の申告義務が生じるため、避けてとおることはできません。
こちらのページでは、相続税申告について「何から手をつければいいの?」「手続きにはどのくらいの時間がかかるの?」などのご不安があるに向けて、相続の発生から相続税申告完了までの流れと、相続税申告を行う際に押さえておきたい注意点をお伝えいたします。
相続の発生~相続税申告までの手続きの流れ
相続税申告は、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に行うもとの定められています。“相続の発生を知った日“とは、基本的には故人(以下、被相続人)が亡くなった当日のことを指します。
実際に身近な方が亡くなると、ご葬儀や供養の手配、四十九日の法要等でめまぐるしく日々が過ぎていきますので、相続税申告に本腰を入れて取り組めるのは実質8か月程度しかないとお考えください。相続の発生から相続税申告の期限まではあっという間に時間が過ぎていった、と感じる方も少なくありません。この短い期間の中に行うべき手続きは膨大かつ多岐にわたりますので、あらかじめしっかりと把握しておきましょう。
1.遺言書の確認

相続では、原則として被相続人の最終意思である遺言書が優先されます。遺言書の有無がその後の相続手続きの進め方に影響するため、相続が発生したらはじめに遺言書が遺されていないかどうか確認しましょう。
2.相続人の調査・相続財産の調査
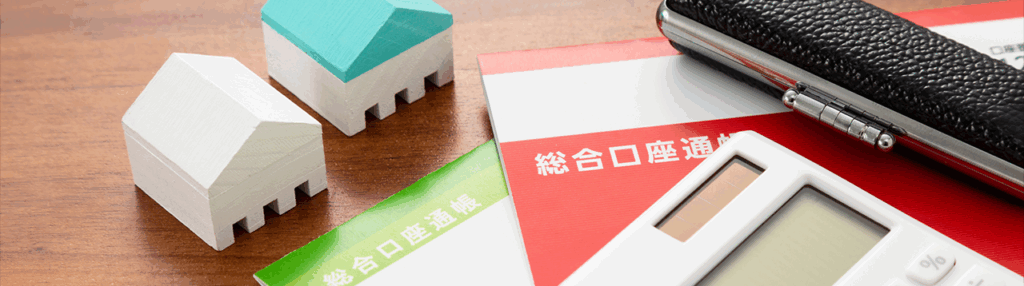
法定相続人(被相続人の財産を取得する法的な権利を有する人)が誰であるか、そして相続の対象となる財産はどのようなものかを調査します。
相続人調査に必要なものは、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍です。この戸籍をもとに「相続関係説明図」を作成し、一目で親族関係がわかるようにしておきましょう。また、被相続人の戸籍収集時に相続人の現在の戸籍も取得しておきます。
次に相続財産の調査ですが、預貯金関連は取引先金融機関、不動産関連は法務局にて財産状況の根拠となる書類を請求します。被相続人が所有していた財産の種類が多ければ、そのぶん取り寄せる書類も増えますので、時間も労力もかかります。
税理士事務所によっては「必要書類はご自身でご用意ください」と、必要書類の収集に対応してくれないケースもあるようですが、一般の方が時間を捻出して平日の日中に各所へ書類請求に出向くのは非常に大変ではないでしょうか。
お忙しくて時間の取れない方、不慣れなのでどこに書類請求の手続きに不安な方のニーズにお応えするため、沖縄相続税申告センターでは書類収集の代行も承っております。もちろん、ご自身で書類収集することも可能ですので、ご希望にあわせてプランをご選択ください。
3.相続財産の評価・財産目録の作成
調査した相続財産の状況から、相続税申告が必要になる見込みがあるときには、相続財産の評価を行い、その価額を明確にしましょう。相続財産の評価は、まさに専門家の力量が試されるところでもあります。
財産評価のなかでも特に難しいとされているのが不動産の評価で、専門家ごとに評価結果に差が生じることも珍しくありません。
また、相続税に設けられた特例や控除は多岐にわたり、それぞれに複雑な要件があります。相続税に関する深い知識を網羅している専門家でなければ適用可否の判断が難しいだけでなく、相続税申告の経験が浅い人ではそもそも相続税額を下げるお得な制度を知らないというケースもあります。これが、「相続税申告は税理士選びが重要」といわれるゆえんでもあります。
相続税額を正しく計算するには、適切な財産評価が欠かせません。財産の評価額が確定したら、「財産目録」という財産の種類や相続税評価額を一覧で明示した書面を作成しましょう。
4.遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
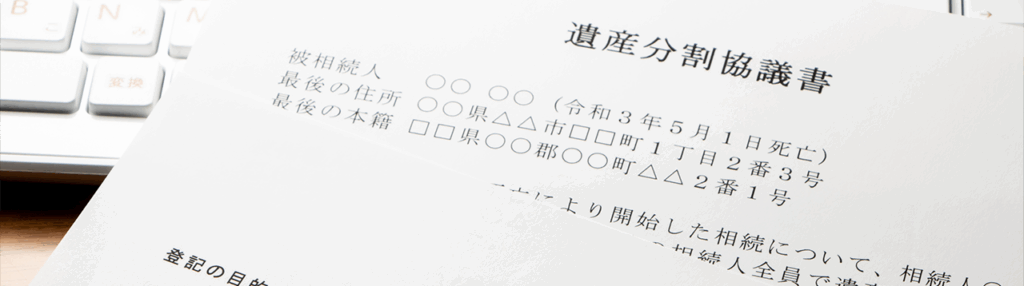
遺言書の無い相続においては、遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するか相続人全員で決める必要があります。協議で相続人全員が合意に達したら、協議結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押します。
なお、相続税申告が必要な場合は、相続税の納税額も考慮に入れて遺産分割方法を考えることが大切です。
将来的に二次相続(例:はじめの相続で配偶者と子が相続した後、配偶者も亡くなり発生した二度目の相続)が発生する可能性はあるか、また、誰が・どの財産を・どの割合で取得するかなど、遺産分割の方法次第で最終的に手元に残る財産額が大きく変わることもあります。
将来も見据えてさまざまなシミュレーションを行い、どのような遺産分割が最適か、相続税申告に精通した専門家のアドバイスを受けながら考えていくとよいでしょう。
5.相続税申告書類の作成・相続税の納付
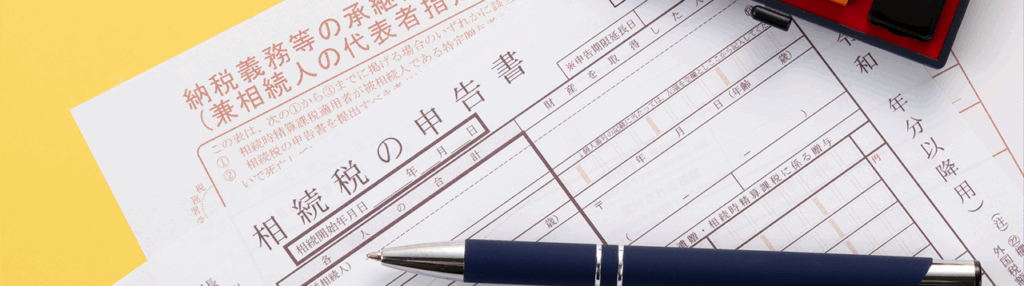
相続税の申告書類を作成し、被相続人の最終住所地を所轄する税務署に申告書類および必要書類を提出します。
相続税の申告時は、相続人を示すための戸籍や、金融機関の残高証明書など、さまざまな書類を申告書類に添付して提出する必要があります。
なお、相続税は現金での一括納付が原則ですが、延納、物納、相続財産(不動産等)を売却し現金化してから納税など、他にも方法があります。相続財産の売却のタイミングも見極める必要がありますので、納税資金の工面に不安がある方は相続税の専門家に相談することをおすすめいたします。
6.預貯金の解約・不動産など各種財産の名義変更手続き
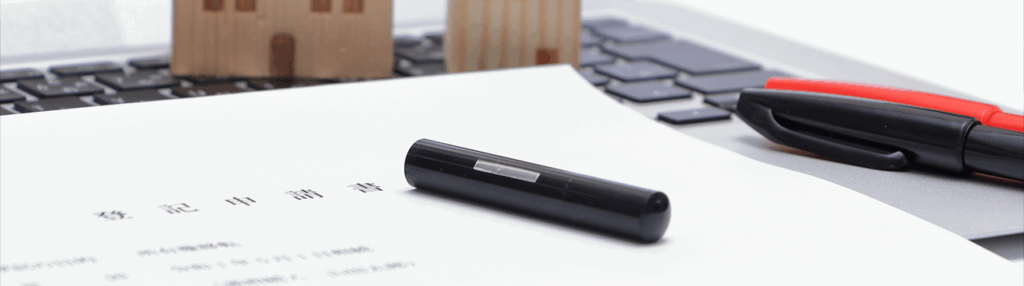
被相続人の財産を取得した人の所有物とするため、各財産の種類に応じて名義変更などの手続きが必要となります。遺産分割協議書の内容に沿って手続きを行いましょう。
なお、相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)の申請は2024年4月より義務化されています。遺産分割の成立から3年以内に申請を行わない場合は過料の対象となることもありますので、相続税申告と同様、こちらも速やかな手続きが必要です。
相続税申告で押さえておくべき注意点
相続税申告には期限が定められています!

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10か月以内に、申告書類を提出し、納税が必要な場合は納税まで完了するものと定められています。
相続税申告が必要にもかかわらず正当な事由なくこの期限を超えると、延滞税や加算税などペナルティが発生するほか、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」などの相続税額の軽減につながるお得な制度を利用できなくなります。
納めるべき税金を最小限に抑えるためには、定められた期限内に適切に相続税申告を完了できるよう、迅速かつ正確に手続きを進めていくことが重要です。
特例等の適用で相続税納税額が0円になったとしても申告は必要!
相続税には納税額を軽減するお得な特例や控除制度があり、適用することによって納めるべき金額が0円になり、相続税を納める必要がなくなることもあります。
「結果として相続税額が0円になるのだから、何も手続きしなくてよいだろう」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
相続税の特例や控除は自動的に適用されるものではありません。特例や控除の適用について相続税申告を行うことではじめて適用されるのです。
特例や控除により相続税額が0円になった時は、納税は不要でも相続税申告は必要ということをしっかりと認識しておきましょう。
不動産の評価は専門家同士でも結果に差が出るほど難しい!

相続税申告では、財産の相続税評価額を明確にする必要があります。例えば土地については「路線価」を用いるなど、財産の種類ごとに定められた評価方法に従って評価します。
財産と同等品の売買価格の相場をもとに「大体このくらいの金額だろう」と、独自の判断で財産の相続税評価額を決めることは大変危険です。場合によっては税務署から指摘を受け、追徴課税が発生し、本来は支払う必要のない税金まで納めることになりかねません。
相続財産の中でも不動産は大きな割合を占めることが多く、不動産の相続税評価額が最終的な相続税額に大きく影響すると考えられます。特に土地については、その形状や立地、周辺環境などにより相続税評価額が変動します。
相続税申告に精通した専門家であれば、その土地のもつ事情を漏れなく考慮に入れ、相続税評価額の低減につながる補正率や特例等を用いて適切に相続税評価額を算出します。相続税評価額を算出するには相続税に関する深い知識が不可欠で、経験豊富な専門家と経験の浅い専門家では、計算結果に大きな差が生じることもあるほど難しい分野なのです。
例えば、補正率等を用いない標準的な評価方法では8,000万円の土地だとしても、専門家が適切に補正し評価することで6,500万円にまで抑えられる、ということも珍しくありません。この場合、相続税額に200万円以上の差が出る可能性もあります。専門家へ支払う報酬額を考慮に入れたとしても、十分お得になるのではないでしょうか。
相続財産に不動産が含まれる場合には、相続税申告の実績が豊富な専門家に依頼することをおすすめいたします。
一般の方がご自身で相続税申告をすると、税務調査のリスクが高くなる?!
税理士ではなく一般の方がご自身で相続税申告を行った場合、税理士が申告に携わった場合よりも税務署によるチェックが厳しくなる傾向があります。これは、一般の方は相続税申告に不慣れなため財産の相続税評価額や相続税の計算、特例等の適用について不備があることが多く、申告した相続税額が過少になっていることが多いと考えられるからです。
相続税申告に不慣れな方が間違いがちな例としては、生前贈与加算(被相続人から生前贈与を受けていた時、一定期間内の贈与を相続財産に持ち戻すこと)を知らずに相続税を計算してしまった、預貯金などの財産の調査漏れがあった、特例の適用要件に該当していなかった、などが挙げられます。
税務調査で不備を指摘されると追徴課税が発生するため、注意が必要です。
本来納めるべき金額よりも多く納税しても、自動的に還付されることはない!
相続税は申告納税制度を採用しています。地方税などは行政が税額を計算して納税者に通知されますが、相続税は納税者側が自ら税額を計算しなければなりません。
気をつけなければならないのが、誤って本来納めるべき金額よりも多く納税したとしても、原則として納税者側が還付や修正の手続きを行わない限り戻ってくることはないという点です。一方で、申告納税額が少ない場合には税務署から指摘され、不足分の追加納税だけでなくペナルティとして延滞税・加算税などさらに多くの税金を支払うことになってしまいます。
相続税申告は、納税額が過剰になることなく、過少になることもなく、適切な相続税額を計算するよう細心の注意をはらう必要がありますので、たとえ税理士であっても相続税に関する深い知識とノウハウを蓄積していなければ対応が困難な専門領域といえます。
相続税申告の経験豊富なプロに依頼するのが確実!
ここまで相続税申告までの手続き流れや押さえておくべき注意点をお伝えさせていただきましたが、相続税申告には考慮すべき点が数多くあり、プロの力を借りなければいかに大変かがおわかりいただけたのではないでしょうか。
相続が発生したら、ご自身で抱え込むことなく、まずは専門家に相談し、どのような手続きが必要になるか具体的にイメージしてみましょう。そのうえで、ご自身で手続きを進めるのか、専門家に依頼するのかを判断されることをおすすめいたします。

沖縄相続税申告センターは沖縄(那覇・中部エリア)の頼れる相続税申告のプロフェッショナルとして、相続税申告に関するご相談やご依頼を多数頂いております。
相続税申告の専門家による初回完全無料相談では、沖縄の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理し、お1人おひとりに最適なお手伝いをさせていただきます。今後必要となる手続き内容や、相続税申告の要否について、私どもがお手伝いする場合のサポートプランや料金など、わかりやすくご案内させていただきますので、ぜひお気軽に沖縄相続税申告センターへお問い合わせください。









